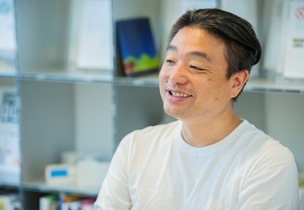とにかく本が好き!が出発点
「ピリカタント」という言葉は耳慣れないけれど、不思議と愛らしく一度聞いたら忘れられない響きです。魔法の呪文のようなこの名前、北海道で生まれ育った店主の西野さんが、“タントピリカ=美しい今日”というアイヌ語をアレンジしてつくった店名です。この店名が象徴するように、日々の美しさや何気ない喜びを見いだせるようにと、ピリカタント書店はオープンしました。
書店がオープンしたのは、2012年の11月。くつろげる雰囲気の店内には、古書、新刊本両方が並び、本以外の雑貨の存在感もなかなかのもの。そして、店内右手のカウンターには、西野さんが漬けたという、ブルーベリーや甘夏など、旬の果物の酵素やシロップの瓶が並んでいます。それらを使ったお手製の飲み物や、西野さんが「みんなのお母さんになった気持ちでつくる」ごはんもピリカタント書店になくてはならない要素です。西野さん曰く「おばあちゃんちに来たみたいっていわれることもある」ほどのゆったりした空間。本と本からこぼれ落ちるさまざまな世界が一緒になって、懐の深い印象を受けます。
西野「とにかく子どもの頃から本が大好きなんです。東京に出てきて文化服装学院に入ったのは、ファッション雑誌に携わりたかったから。大量生産で消費のサイクルも早い業界に疑問を感じましたが、卒業後は、本が好きという基本に立ち帰り、いくつかの会社で編集のアルバイトを経験しました。その後、『ごはんとくらし』をテーマに出版を続けるアノニマスタジオに入社して、生きることと本気で向き合う姿勢を先輩や著者から学びました。本を編集するとき、“あなたの根っこはなんなの?”と問われる場面がすごく多いんです。正解や良し悪し求めるのではなくて、自分が求めるものを体現していくことは、お店をやるようになった今でも大事にし続けていることです。共感や夢を伝えるパイプ役という意味では、編集者だった自分と、本屋の役割は何も変わっていないんです」
アノニマスタジオを退職した後は、アルバイトでお金を貯めては旅、またアルバイトしては旅、という日々を送っていたという西野さん。その2年半ほどの間に世界各国に足を運んで、さまざまな見聞を広げました。しかし、旅から得た結論は意外なもの。「非日常を求めて外へ外へと行っても、心が動くのは夕日だったり、初めて海の中で見た海底だったり、何気ない食事だったり、日常にあるものなんだなと気づいたんです」と西野さんは言います。そして、毎日の中に旅の要素があればすてきだし、本を開くといつも旅の気分を味わえるから本が好きなのだと改めて思ったそう。そしてその想いがピリカタント書店の原型になりました。




下北沢の物件と運命の出合い
西野さんは、いつかは自分のお店を持ち、日常にいながらにして旅情が味わえたり、ほっと一休みして日々の中のすてきに気づけたりする空間をつくりたい、という想いを親友に打ち明けました。すると、しばらくして、その親友が思いがけず下北沢の物件を紹介してくれました。
西野「最初は今すぐ何かやりたいというわけではないし、やるならもっと自然のある場所がいい、と思っていたんですが、せっかく紹介してくれたので、見てみるだけのつもりで行ったんです。そしたら“ここだ!”と思ってしまいました。お店に対するアイデアがどんどん生まれ、その日は眠れなかったくらいです」
下北沢駅から歩いて5分ほど。想い描いた理想の場所とはほど遠かったはずなのに、恋に落ちてしまったその部屋は、今になってみれば自分のやりたいことにぴたりと寄り添う物件だったのです。
西野「学生時代は友だちと集まる拠点が下北でしたが、いろいろな人種が行き交う町というイメージでした。下北を目指してみんな来るような。けれど、お店を始めてそのイメージが変わりました。もちろん遊びに来る人も多いけれど、生活がよく見える町なんです。暮らしている人も多いし、いい意味で人間くささがある。お金を持っているかいないかとか肩書きとかいう価値観ではなくて、下北沢には自分の道徳の中で生きている人が多い気がします」


内装も、本や雑貨も、ごはんも、
背景が分かるもので
さて、「真っ白い箱」だった元ギャラリーカフェは、どうやって窓が大きくて明るく、ブランコまである(!)本屋へと生まれ変わったのでしょう。
西野「本当にお金がなかったので、世田谷区産業振興公社の創業支援資金制度を利用しました。絶対に無理だとみんなに言われたけれど、正しいことをやっているのだし、審査に通らないはずはないと信じて、あきらめませんでした(笑)」。
西野さんの真っ直ぐな気持ちは通じ、めでたく融資が決定。空間デザインと内装は、友人でもあり世田谷区若林に店を構える、noteworksにお願いしたのをはじめ、さまざまな友人の力を結集してお店ができあがりました。「友人たちや友人が運んでくれる縁がなかったら、お店は続いていません」と西野さんはいいます。
西野「お店が完成することもないと思うんです。背景を知っているもの、きちんと思い入れがあるものを扱うことは柱に据えつつ、自分も学びながら、柔軟にあり方は変化させていきたいですね。本では伝えきれないことも、イベントや雑貨を通して伝えて、さらにこれからは例えば自分でリトルプレス(zine)をつくったりして何かを発信していけたらいいですね。それに本とのかかわり方もいろいろあっていい。レンタルする試みも始めているんですよ」


西野さんの感性が媒介となって、お客さんは、本からにじみ出る旅情や日常の中の喜びと出合い、また日常に戻っていきます。今後さらに、暮らす人、行き交う人々の止まり木的な場所として「生活のにおいのする」下北沢の日常の景色のひとつになっていくのが楽しみな本屋さんです。