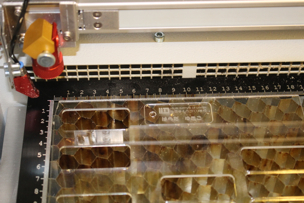第73回「技研公開2019」ワクからはみ出せ、未来のメディア
◇NHK放送技術研究所(技研)の最新の研究成果を一般に公開する「技研公開2019」を、5月30日(木)~6月2日(日)の4日間の日程でで開催します。
◇「ワクからはみ出せ、未来のメディア」をテーマに、3DテレビやAR・VRを活用した、
従来のテレビのワクを超えた視聴サービスを実現する技術など24項目の研究成果を展示します。
表現空間を誇張した多様なコンテンツやサービスの実現を目指した「リアルティーイメージング」の研究成果からは、
高精細VR映像や、AR技術を活用したテレビ視聴サービス技術などを展示します。
日 時:2019年5月30日 (木)~ 6月2日 (日)
午前10時~午後5時(入場は終了の30分前まで)
会 場:NHK放送技術研究所
東京都世田谷区砧1-10-11入場
入場料:無料
H P:https://nhk.or.jp/strl/open2019/
◆展示項目
●2030~2040年ごろのメディア技術
●ARを活用したテレビ視聴スタイル
●ネット×データ×IoTが連携するメディア技術
●スポーツ映像の状況理解技術
他※詳細はhttps://www.nhk.or.jp/strl/open2019/tenji/index.html
◆講演(技研講堂にて)
◇5月30日(木)午前
●基調講演
「身体の未来 拡張現実感から人間拡張工学へ」
東京大学 先端科学技術研究センター 教授 稲見昌彦氏
●基調講演
「空間表現を広げる視覚のしくみ」
東北大学 電気通信研究所 所長・教授 塩入諭氏
◇5月31日(金)午前
●ラボトーク
技研職員によるプレゼンテーション6件
◆ガイドツアー
◇6月1日(土)、2日(日)
●研究員が解説するツアーやお子さまを対象としたイベントも開催します。
◎詳しくはこちらのHPでご確認ください。
https://nhk.or.jp/strl/open2019/