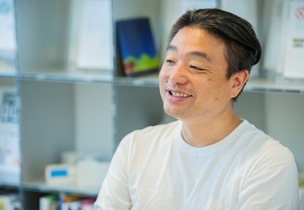年別アーカイブ: 2013年
文化もユニバーサル化へ、世田谷パブリックシアターの出張公演

いつものホールが別世界に
この日やってきたのは、上北沢ホーム/デイ・ホーム上北沢という、入居している方と、日帰りのデイサービスを受けている方の両方がいらっしゃる施設。1日に平均45名のデイサービス利用者がいる施設で、世田谷区では2、3番目に大きな規模のホームです。
この日公演の舞台となったのは、一階のレクリエーションホール。会場までゆっくりと歩いてくる方、車椅子に乗っていらっしゃる方さまざまですが、続々とお年寄りが集まり、60名ほどの観客がホールに並びました。
公演が始まるまでの間、前座は職員の方が務めます。「最近は雨が多いんだか少ないんだかよく分からない天気ですけれども…」と始まり、芸達者な話術でお年寄りたちの関心をひきます。
そしていよいよ「@ホーム公演」の新作、『きみといつまでも〜わたしのお父さんはロボットです〜』(ノゾエ征爾さん脚本/演出/出演)が開幕します。この作品のストーリーは「森に住む女の子とロボットお父さんのちょっと変わった親子と、ふたりをとりまく青年と動物がおりなす、ドタバタ人情物語!(資料より)」というもの。しかし大掛かりな舞台セットはなく、観客の前に置かれているのは黒板だけです。開演前は、状況がよく飲み込めず、ポカンとしている方も目に付きましたが、その不安はすぐに吹き飛ぶことになりました。


上演に施された工夫の数々
というのも「@ホーム公演」では、お年寄り向けにさまざまな工夫がされています。まず劇の始まりには、皆の顔見知りである職員さんが前座を務めた後、扮装して出演し、場を和ませます。その後登場した4人は全員がプロ。出番になると自己紹介し、役名を黒板に大きく書きます。滑舌(かつぜつ)のいい話し方、平易な言葉づかい、そして黒板を使った文字の補助など、耳が不自由な方や理解に時間のかかる方に配慮ある演出のお陰でぐっと観客が前のめりになったのを感じました。
ほかにも、世界的なパントマイミスト山本光洋さんによる、見事なロボットの動きや、「三百六十五歩のマーチ」「君といつまでも」をはじめとする懐メロに、観客はみるみる惹き込まれていきました。舞台セットの黒板も、役者が隠れる場になったり、人形劇の舞台になったりと大活躍。また、お年寄りがパントマイムに一部参加するような仕掛けも、会場を沸かせます。随所にこれでもかと引き込まれる要素がてんこもり。しかも演じるのは、世田谷パブリックシアターほか各地で活躍するプロの演出家や俳優たちです。ストーリーや演技のクオリティを保ちつつも、直観的でわかりやすい、すばらしい舞台をつくりあげていました。


プロの演技に顔がほころぶお年寄り
始まる前は「何を言っているのか分からない」と不安がっていたおばあさんも、始まってみるとケラケラ笑っていたり、微動だにせずじっと見入っていた方が、「朧月夜」が流れた瞬間に、はっきりと美しい声で口ずさんだり。皆うんうん頷きながら体を揺らし、さまざまに楽しんでいました。「君といつまでも」は全員で大合唱となり、最後には涙を流す人もあちこちに見られました。「来てもらってありがたかった」「本当にかわいかったねぇ」「飽きさせないからすごい」と、客席のあちこちからの感謝の声とともに、30分の夢の時間は終わりました。

アウトリーチ演劇の意義
観劇を終え、この4月から上北沢ホームの施設長を務める、木谷哲三さんにお話をうかがうことができました。木谷さんは、以前は世田谷パブリックシアターも管轄する世田谷文化生活情報センターの副館長で、平成22年から始まった第一弾「@ホーム公演」を実現させた立役者の一人でもあり、今回のような公演の意味を当事者として実感されている方です。
木谷「もともと世田谷パブリックシアターでは、劇場を飛び出して芸術を生活の中に取り入れるような活動を目指してきました。しかし、施設に入所されているようなお年寄りには、なかなか演劇を届けることができませんでした。一方で、世田谷パブリックシアターにとって、若手演出家の育成事業も大事な役割です。そこがマッチしたのが、当時まだ新人だったノゾエ征爾さんが新作をつくり、老人ホームを巡回するという試みでした」
前作の『チャチャチャのチャーリー〜たとえば、恋をした人形の物語〜』は、3年かけてのべ30施設で公演、1800人の方々が鑑賞したといいます。この日こけら落としだった新作も、重度障がい者施設を含め、名乗りを挙げた世田谷区内11ヵ所の施設を、2週間かけて回ります。
木谷「介護の現場にも、本物を提供すること、そしてそれが《演劇》である点もポイントです。芝居は、意図的に感情を増幅させて表現しますよね。それがいいんです。普段あまり笑わない認知症の方が大笑いしたり、落ちつきのない方が集中して観劇したり、いつもと違う表情が引き出される。演劇には、セラピーとしての可能性もあるのだと実感しています」



もちろん、お年寄りの方々だけでなく、演出家、俳優をはじめとしたスタッフにとっても、この巡回公演はいい経験です。「観客と一緒にいい舞台ができる」といわれる演劇の現場。閉じた蓋が開くように感情を表に出して観劇するお年寄りの方々とつくる舞台は、格別な喜びがあるそうです。
木谷「@ホーム公演であっても、世田谷パブリックシアターでやる演劇と、何ら変わりない手順で作品づくりをしていますよ。スタッフもみなプロです。文化もユニバーサルデザインの時代。本物を、今まで届きにくかった人の元へきちんと届けることが大事な時代になってきています」
木谷さんがいうように、日常生活の中に潤いを与える芸術の楽しみは、日常生活が困難なところにこそ、必要とされています。今のところ、東京都内で「@ホーム公演」のような取組みをしている区は、他にありません。世田谷パブリックシアターが贈る夢いっぱいの演劇は、施設にいる方々を楽しませることはもちろん、福祉の文化化、文化のユニバーサル化、両方の課題に応える手法として、今後さらに重要な役割を担っていくのではないでしょうか。
(撮影:庄司直人 )


世田谷パブリックシアター@ホーム公演
『きみといつまでも ~私のお父さんはロボットです~』
脚本/演出=ノゾエ征爾
出演=山本光洋、たにぐちいくこ、井本洋平、ノゾエ征爾
Felix 中澤清香
人の営みが交差する、旅と暮らしの本屋「ピリカタント書店」

とにかく本が好き!が出発点
「ピリカタント」という言葉は耳慣れないけれど、不思議と愛らしく一度聞いたら忘れられない響きです。魔法の呪文のようなこの名前、北海道で生まれ育った店主の西野さんが、“タントピリカ=美しい今日”というアイヌ語をアレンジしてつくった店名です。この店名が象徴するように、日々の美しさや何気ない喜びを見いだせるようにと、ピリカタント書店はオープンしました。
書店がオープンしたのは、2012年の11月。くつろげる雰囲気の店内には、古書、新刊本両方が並び、本以外の雑貨の存在感もなかなかのもの。そして、店内右手のカウンターには、西野さんが漬けたという、ブルーベリーや甘夏など、旬の果物の酵素やシロップの瓶が並んでいます。それらを使ったお手製の飲み物や、西野さんが「みんなのお母さんになった気持ちでつくる」ごはんもピリカタント書店になくてはならない要素です。西野さん曰く「おばあちゃんちに来たみたいっていわれることもある」ほどのゆったりした空間。本と本からこぼれ落ちるさまざまな世界が一緒になって、懐の深い印象を受けます。
西野「とにかく子どもの頃から本が大好きなんです。東京に出てきて文化服装学院に入ったのは、ファッション雑誌に携わりたかったから。大量生産で消費のサイクルも早い業界に疑問を感じましたが、卒業後は、本が好きという基本に立ち帰り、いくつかの会社で編集のアルバイトを経験しました。その後、『ごはんとくらし』をテーマに出版を続けるアノニマスタジオに入社して、生きることと本気で向き合う姿勢を先輩や著者から学びました。本を編集するとき、“あなたの根っこはなんなの?”と問われる場面がすごく多いんです。正解や良し悪し求めるのではなくて、自分が求めるものを体現していくことは、お店をやるようになった今でも大事にし続けていることです。共感や夢を伝えるパイプ役という意味では、編集者だった自分と、本屋の役割は何も変わっていないんです」
アノニマスタジオを退職した後は、アルバイトでお金を貯めては旅、またアルバイトしては旅、という日々を送っていたという西野さん。その2年半ほどの間に世界各国に足を運んで、さまざまな見聞を広げました。しかし、旅から得た結論は意外なもの。「非日常を求めて外へ外へと行っても、心が動くのは夕日だったり、初めて海の中で見た海底だったり、何気ない食事だったり、日常にあるものなんだなと気づいたんです」と西野さんは言います。そして、毎日の中に旅の要素があればすてきだし、本を開くといつも旅の気分を味わえるから本が好きなのだと改めて思ったそう。そしてその想いがピリカタント書店の原型になりました。




下北沢の物件と運命の出合い
西野さんは、いつかは自分のお店を持ち、日常にいながらにして旅情が味わえたり、ほっと一休みして日々の中のすてきに気づけたりする空間をつくりたい、という想いを親友に打ち明けました。すると、しばらくして、その親友が思いがけず下北沢の物件を紹介してくれました。
西野「最初は今すぐ何かやりたいというわけではないし、やるならもっと自然のある場所がいい、と思っていたんですが、せっかく紹介してくれたので、見てみるだけのつもりで行ったんです。そしたら“ここだ!”と思ってしまいました。お店に対するアイデアがどんどん生まれ、その日は眠れなかったくらいです」
下北沢駅から歩いて5分ほど。想い描いた理想の場所とはほど遠かったはずなのに、恋に落ちてしまったその部屋は、今になってみれば自分のやりたいことにぴたりと寄り添う物件だったのです。
西野「学生時代は友だちと集まる拠点が下北でしたが、いろいろな人種が行き交う町というイメージでした。下北を目指してみんな来るような。けれど、お店を始めてそのイメージが変わりました。もちろん遊びに来る人も多いけれど、生活がよく見える町なんです。暮らしている人も多いし、いい意味で人間くささがある。お金を持っているかいないかとか肩書きとかいう価値観ではなくて、下北沢には自分の道徳の中で生きている人が多い気がします」


内装も、本や雑貨も、ごはんも、
背景が分かるもので
さて、「真っ白い箱」だった元ギャラリーカフェは、どうやって窓が大きくて明るく、ブランコまである(!)本屋へと生まれ変わったのでしょう。
西野「本当にお金がなかったので、世田谷区産業振興公社の創業支援資金制度を利用しました。絶対に無理だとみんなに言われたけれど、正しいことをやっているのだし、審査に通らないはずはないと信じて、あきらめませんでした(笑)」。
西野さんの真っ直ぐな気持ちは通じ、めでたく融資が決定。空間デザインと内装は、友人でもあり世田谷区若林に店を構える、noteworksにお願いしたのをはじめ、さまざまな友人の力を結集してお店ができあがりました。「友人たちや友人が運んでくれる縁がなかったら、お店は続いていません」と西野さんはいいます。
西野「お店が完成することもないと思うんです。背景を知っているもの、きちんと思い入れがあるものを扱うことは柱に据えつつ、自分も学びながら、柔軟にあり方は変化させていきたいですね。本では伝えきれないことも、イベントや雑貨を通して伝えて、さらにこれからは例えば自分でリトルプレス(zine)をつくったりして何かを発信していけたらいいですね。それに本とのかかわり方もいろいろあっていい。レンタルする試みも始めているんですよ」


西野さんの感性が媒介となって、お客さんは、本からにじみ出る旅情や日常の中の喜びと出合い、また日常に戻っていきます。今後さらに、暮らす人、行き交う人々の止まり木的な場所として「生活のにおいのする」下北沢の日常の景色のひとつになっていくのが楽しみな本屋さんです。
世田谷という「地域」と暮らす人の「顔」をつなぐ取り組み

世田谷という「ローカル」を知り、守るために
「三軒茶屋」の地名は、その名の通りかつてその土地に三軒の「お茶屋」があったことに由来しています。人口88万人が暮らす世田谷区には三軒茶屋のように全国的にも有名な地域も多く、いわゆる「地域活性」という言葉からは遠く思えてしまうもの。しかし、誰もが知っているエリアでも、路地に入るとシャッターが閉じた通りや、知らなければ通りすぎてしまうような小さな商店も数多く存在しています。
そんな世田谷では、ここをひとつの「地域=ローカル」と捉え、地域と人とのつながりを深めようとする取り組みが行われています。今年の2月と5月に連続開催された「世田谷ビジネス伝承フェア」は、世田谷地域に根付く地域ビジネスの実情を知り「廃業」から守ろうとするイベント。2月のトークイベントには、若い女性からご年配の方まで地域に興味のある幅広い層が集まり、イベントを主催する特定非営利法人カプラー代表の松村拓也さんによる司会進行のもと「世田谷のビジネス」について語り合われました。
区内でさまざまなビジネス講座を開催している松村さんは「仕事は社会の財産であるという考えがありますが、ビジネスそのものも社会の財産です」と語り、「ビジネスの廃業には”儲からないこと””跡継ぎがいないこと””将来性がないこと”の3つが原因にあります。人口88万人が暮らす世田谷区でも、跡継ぎがみつからずに廃業することや、将来性がないために諦めてしまうことが多いんです」と世田谷に存在する課題を提示。「地域の財産を守るために、まず問題を話すことが重要です」と語ります。


太子堂「八幡湯」と下北沢「しもきた茶苑」の話
「ビジネス伝承フェア」では、実際に地域ビジネスを営んでいるご本人がその実情について語ります。太子堂にある銭湯「八幡湯」の金山喜久雄さんは、銭湯の旦那衆が集まって民謡や踊りを披露する集団「銭湯ダンナーズ」のひとり。銭湯という商いについて「うちの銭湯では毎日徹底的に掃除をやっております。自慢ではないけど世田谷で一番きれいな自信もあります」と陽気に語りながらも、近年の状況について「かつては都内に2800件も銭湯があり、日曜日は1000人、平日でも600〜700人ものお客さんが来ていて、それぞれが儲かっていました。しかし最近は1日に100人も来ないことがある」と厳しさを語りました。
下北沢で代々続くお茶屋を営んでいる「しもきた茶苑」の大山泰成さんは、一般には聞き慣れない「茶師」としても活躍される方。「かつて下北沢もお茶の産地だったことがありました」と、お茶と地域を知る大山さんの話では、黒船来航から海外への輸出品として栄えはじめたお茶は、昭和30年代頃から国内消費がはじまったことで「お茶屋」が増加したとのこと。しかし、昭和20〜30年代には下北沢だけで10軒以上あったお茶屋も、今は2軒になったと言います。
「お茶屋の繁栄はここ50〜60年の繁栄のことだから、なくなることもある。自分が努力しなければ消えてしまうこと、私たちは肝に命じながらビジネスをしています」と、厳しさを冷静に語りながら仕事人としての熱も伝えてくれました。
「ビジネス伝承フェア」ではスピンアウト企画として、5月に「しもきた茶苑」を訪れてのお茶会も開催しました。お茶会で大山さんは、日本に9人しかいない茶師のひとりとして、普段はなかなか知ることができないお茶屋のことや、美味しいお茶の飲み方を披露し参加者からは「スーパーで買うだけでは分からない貴重な話が聞けた」と好評を博しました。



暮らす人と地域の「顔」が見えるように
きっかけさえあれば「こんなに身近にプロフェッショナルがいたんだ」と心強く感じられる、すぐそばにある銭湯やお茶屋も知らないままだとつい通りすぎてしまい、お互いの存在をなんとなく知らないまま無関心になってしまうもの。
「ビジネス伝承フェア」を運営する皆本徳昭さんは「震災以降、多くの人が自分の足元をみるようになりました。実際、震災時にはスーパーからお米がなくなりましたが、お米屋さんにはお米がたくさんありました。でも、お米屋さんは常連さんに売れるようにシャッターは閉めていた。それが地域にとって何よりのセーフティネットだと思います。インターネットに出ているだけじゃなく、本当の意味で”顔が見えているか”が大事です」と人と地域がつながることの大切さを語ります。
世田谷区には日本全国からの転入者も多く、もともと地元ではない人も多く暮らしている分、世田谷という地域とつながるきっかけがないまま過ごしてしまう人は少なくありません。「伝承フェアは、地域で商売をする方と地域に暮らす人が知り合う機会にもなります」と皆本さん。
こうしたきっかけが、世田谷の課題を解決するひとつ方法となり、世田谷と区民のよりよい関係を築いていくはず。「これまでは商店街にお店を出している方が、どんなことを考えているか分からなかったけれど、もっと相談すればいいんだと思った」という参加者の声にも、取り組みへの期待が現れていました。



まちのセラピストとして愛される店も。大井町線の花屋さん
うっとうしい梅雨も楽しもう!初夏の風物詩「アジサイ」
食べてにっこり、お腹も満足な豪徳寺のテイクアウトグルメ
miaozi
紙でつくるミニチュア、1/100の世界「テラダモケイ」

テラダモケイとは
テラダモケイの「1/100建築模型用添景セット」は、模型といっても実にリアル。自動販売機に「たばこ」の文字がちゃんと入っていたり、ガードレールには東京都のイチョウのマークが!また、人物の配置やポーズなどをさまざまに表現できるのが魅力で、土下座やプロポーズ、酔っ払いのおじさん、自転車で出前を急ぐ人など、つくる人によって、さまざまな街の光景を演出できる面白さがあります。
シート1枚ごとにテーマがあり「水辺の公園編」「工事現場編」など街の風景を切り取ったものや「お花見編」「クリスマス編」などの季節もの、「東京編」「NY編」などの都市シリーズも。およそ月1本のペースで新作を発表してきて、現時点(2013年6月)でNo.34の最新作「バンコク編」まで揃っています。
バンコク編には、年老いた犬やトゥクトゥクなど、これまた現地に暮らす人の視点で切り取られた風景が広がります。
寺田「みんな知ってはいるけど、普段気にもとめないような風景を敢えて表現することで、“あるあるある”と共感してもらえたりするんですよね。」


建築設計の仕事とテラダモケイは
最終目的が同じ
もともとこの添景セットは、建築家である寺田さんが、建築模型につける添景を作り置きしようと考えたのが始まりでした。
寺田「模型を素敵に見せるには、建物そのものよりも周りに配置する“添景”といわれる人や家具、街路樹といったものが重要なんです。でも徹夜で模型をつくっていると、肝心の添景をつくる頃には疲れ果ててしまうことがよくあります。そこで、この添景をあらかじめ量産しておければいいなと思ったんです」
寺田設計事務所では、建物の建築設計や、プロダクトデザインなどの仕事を主に手がけています。寺田さんが感じてきたのは、家をつくるうえで、設計は最終目的ではなく手段に過ぎないということ。本来の目的は、その家で家族と楽しくご飯を食べたり、コミュニケーションしたりといった人の営みをデザインすることだと言います。
寺田「でも設計ばかりやっていると、その本来の目的を忘れちゃうことがあるんですよね。一方で、このテラダモケイは人の日常やコミュニケーションを直接表現するものなので、設計の仕事と同じくらい大事にしています。テラダモケイも建築設計も、表現方法は違いますが、実現したいことの最終目標は同じなんです」
直営店を開いた理由も、テラダモケイのシリーズが増え過ぎて全シリーズ見られる場所が欲しかったということに加えて、直接リアルなお客さんと接してみたいという思いが強かったのだそう。土日には寺田さんがエプロンをかけて店頭に立っていることもあるので、ふらりとお店に入ってみるとご本人に会えるかもしれません。



下北沢を選んだわけ
テラダモケイは、下北沢の劇場「ザ・スズナリ」の並びの脇道を奥へ進んだ左手にあります。もともと新宿に事務所をかまえていた寺田設計事務所が、オフィス兼直営店の場所として下北沢を選んだのには、明確な理由がありました。
寺田「下北沢って無目的に歩いている人が多い気がしたんですよ。例えば、青山や代官山のような街は、ブランド店の存在感が強くて、ブランド目的で街を訪れる人が多いですよね。でも下北沢では、若いカップルなど店にふらりと入ってもらえるイメージがあったんです。それに青山で一日過ごすのは結構疲れるじゃないですか。でも下北沢なら、余計な気をはらずに地に足をつけて過ごせる感じがしました」
最近土日をつかって、お客さんと一緒にテラダモケイを組み立てるワークショップも始めたのだそう。寺田さんにとっても意外だったのは、テラダモケイは大人向けにつくった商品なのに、子どもたちが夢中になることでした。
「先日開いたワークショップでは、意外とご近所さんの参加が多かったんですよね。私たち自身もこの下北沢の地域コミュニティの一員として、地元のファンの方々と仲良くやっていけたらいいなと思います」と、嬉しそうに話す寺田さん。
テラダモケイを通じて、お客さんとの交流が生まれたことも、人の暮らしをデザインする設計の仕事に、大きな意味がありそうです。
不思議な吸引力をもつ下北沢という街に、またひとつ面白い店が加わりました。
(撮影:上から3番目の「屋台編」の写真のみKenji MASUNAGA、それ以外の写真すべて庄司直人 )